プログラムを終了させる!Pythonでexitを使う方法を現役エンジニアが解説【初心者向け】
初心者向けにPythonでexitを使う方法について解説しています。プログラムを終了する際に使用しますが、いくつか種類があるのでそれぞれ紹介しています。実際にサンプルプログラムを書いているので、参考にしてみてください。
テックアカデミーマガジンは受講者数No.1のプログラミングスクール「テックアカデミー」が運営。初心者向けにプロが解説した記事を公開中。現役エンジニアの方はこちらをご覧ください。 ※ アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 調査期間:2021年8月12日~8月16日 調査対象:2020年8月以降にプログラミングスクールを受講した18~80歳の男女1,000名 調査手法:インターネット調査
今回は、Pythonでexitを使う方法を解説します。
exitは、プログラムを途中で終了させる際に使用します。
exitの種類ごとに書き方を説明しているので、役割も合わせて理解しておきましょう。
目次
なお本記事は、テックアカデミーのPythonコースの内容をもとに紹介しています。
Pythonのexitとは
PythonのexitはPythonのプログラムを終了するためのメソッドです。
Pythonのexitにはいくつか種類があります。
今回は、こちらの3種類の終了方法について解説します。
- exit( )で、REPLのようなインタラクティブシェルを終了する
- sys.exit( )で、Pythonプログラムを終了する
- os._exit( )で、Pythonプログラムを終了する
1. exit( )
exit( )では、REPLの処理を終了させることができます。
コマンドプロンプトを起動してPythonをREPLで実行できる状態にしてください。
REPLというのは、1行の命令の結果を即時表示してくれるメリットがあります。
コマンドプロンプトでPythonを実行する方法に関しては、次の記事を参考にしてみてください。
Pythonの開発環境の導入とコマンドプロンプトでの実行方法を現役エンジニアが解説【初心者向け】 | TechAcademyマガジン
2. sys.exit( )
sys.exit( )では、プログラム自体を終了させることが可能な上、終了ステータスも返すことができます。
処理内容としては例外を発生させて、Pythonプログラムを終了させます。
3. os._exit( )
os._exit( )はあまり使用されることはありませんが、例外処理などを行わず、即Pythonプログラムを終了します。
Pythonでexit( )を使う方法
Pythonでexit関数を使用する場合はexit( )のように記載します。
以下でexit( )を使ってサンプルプログラムを書いているので、参考にしてみてください。
exitを書いてみるプログラムソースコード
print('test')
exit()
表示結果

プログラムの説明
1行目では、testという結果を表示するために、print(‘test’)と記載しています。
今回は、exit( )を利用してプログラムを終了することが目的であるため、1行目には何を記載しても構いません。
2行目では、1行目のプログラム、print(‘test’)の結果である、testが表示されています。
3行目では、exit( )を実行しています。
これによりREPLの処理を終了できます。
Pythonでsys.exit( )を使う方法
Pythonでsys.exit関数を使用する場合はsys.exit(0)のように記載します。
一般的に0を返すと正常終了し、1を返すとエラー終了です。
sys.exit()
以下でsys.exitを使ってサンプルプログラムを書いているので、参考にしてみてください。
sys.exitを書いてみるプログラムソースコード
import sys
for i in range(100):
if i == 1:
print("1です")
sys.exit()
print(i)
表示結果
プログラムの説明
1行目のimport sysでは、sysモジュールをimportしています。
2行目のfor i in range(100):では、繰返し(for)、0から100までの数字を(range(100))、変数iに代入しています。
3行目のif i == 1:では、変数iの中身が1であればという条件文です。
4行目のprint(“1です”)では、3行目の条件に合致すれば、1ですという内容が表示されます。
今回は2回目のfor文処理で数字の1が変数iに代入され、1ですと表示されます。
5行目のsys.exit( )で正常に終了したステータスを返します。
表示自体はされません。
6行目では3行目のif文に合致しなかった場合の変数iが表示されます。
今回は最初の数字である0が表示されます。
コスパとタイパ、両方結果的に良くなる良くなる学び方とは?
「スクールは高いし時間も縛られて効率が悪い」と考える方は多いと思います。
もちろん、時間も費用もかかることは間違いありません。
ただ
結果的に無駄な学びにお金も時間もかける方がリスクが高いという考えもあります。
コスパ・タイパ最適化の参考として、
テックアカデミー卒業生がスクールを選んだ理由
をご紹介します。
- ・困ったときに、質問や相談できる相手がいるため挫折しなかった
- ・プロとして必要なスキルのみを深く学べたので無駄がなかった
- ・副業案件の提供と納品までのサポートがあったので目的を達成できた

安価・短期間で広く浅く学んでも意味がありません。
本当に自分の目的が達成できるか、それが重要です。
自分にどのスキルや学び方が合っているか、どんな学習方法かなど、お気軽に
無料相談
に参加してみませんか?
カウンセラー・現役のプロへ、何でも気軽に無料相談可能。
30分か60分お好きな時間が選べて、かつ3回まで
すべて無料で
ご利用できます。
無理な勧誘は一切ない
ので、お気軽にご参加ください。
この記事を監修してくれた方
| 中本賢吾(なかもとけんご) アジマッチ有限会社 代表取締役社長 開発実績:PHPフレームワークによるフランチャイズ企業向け会員制SNS。Shopifyによる海外進出用大規模ネットショップ構築。Vue.jsによる金融機関向け内部アプリ。AWSやLinuxハウジングサーバでの環境構築。人工知能を利用した画像判別システム。小売チェーン店舗用スマホアプリ。Wordpressによる不動産チェーン店向け賃貸・売買仲介システム。基幹システム移管用データコンバートシステム。 小学生がUnityでオリジナルAndroidアプリをGoogle Playでリリース、NHK Whyプログラミング入賞、全国Programing Festival入賞、中学生がノーコードでSNS型PWAアプリリリースなど、ボランティアプログラミング教育活動行っている。 |
今回はPythonでexitを使う方法を解説しました。
入門向けPythonの学習サイトも記事にしているので、学習したい方は参考にしてみてください。
Pythonを学習中の方へ
これで解説は終了です、お疲れさまでした。
- つまずかず「効率的に」学びたい
- 副業や転職後の「現場で使える」知識やスキルを身につけたい
プログラミングを学習していて、このように思ったことはありませんか?
テックアカデミーのPythonコースでは、第一線で活躍する「プロのエンジニア」が教えているので、効率的に実践的なスキルを完全オンラインでしっかり習得できます。
合格率10%の選考を通過した、選ばれたエンジニアの手厚いサポートを受けながら、人工知能(AI)や機械学習の基礎を完全オンラインでしっかり習得できます。
まずは一度、無料体験で学習の悩みや今後のキャリアについて話してみて、「現役エンジニアから教わること」を実感してみてください。
時間がない方、深く知ってから体験してみたい方は、今スグ見られる説明動画から先に視聴することをおすすめします!
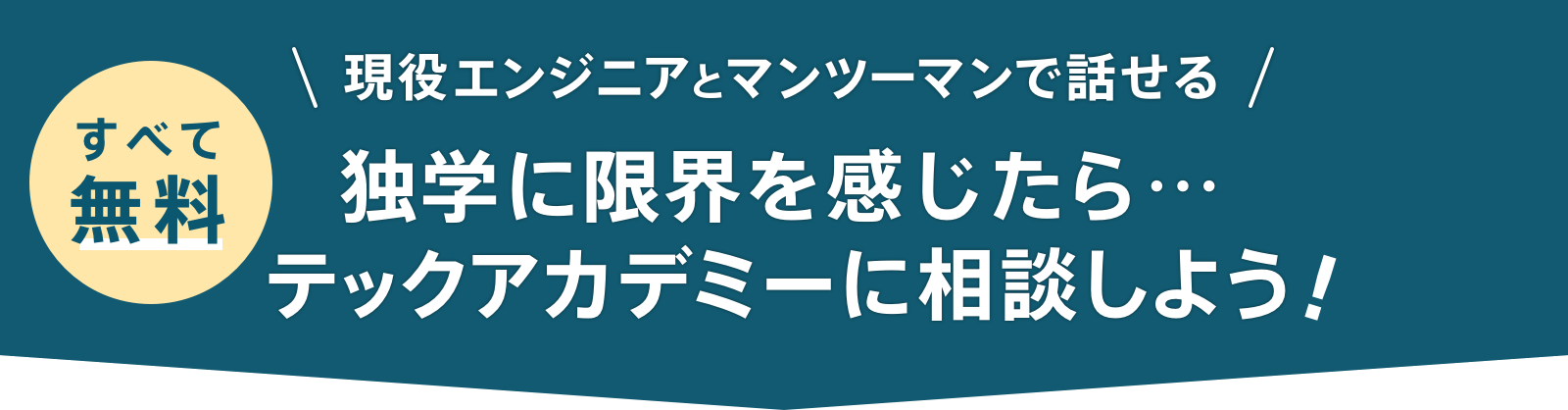
プログラミングを独学で学習していて、このように感じた経験はないでしょうか?
- ・調べてもほしい情報が見つからない
- ・独学のスキルが実際の業務で通用するのか不安
- ・目標への学習プランがわからず、迷子になりそう
テックアカデミーでは、このような
学習に不安を抱えている方へ、マンツーマンで相談できる機会を無料で提供
しています。
30分間、オンラインでどんなことでも質問し放題です。
「受けてよかった」と感じていただけるよう
カウンセラーやエンジニア・デザイナー
があなたの相談に真摯に向き合います。
「自分に合っているか診断してほしい」
「漠然としているが話を聞いてみたい」
こんなささいな悩みでも大丈夫です。
無理な勧誘は一切ありません
ので、まずはお気軽にご参加ください。
※体験用のカリキュラムも無料で配布いたします。(1週間限定)











