HTMLでコードを表示する方法【初心者向け】
HTML初心者向けに、【codeタグ】を使ってコードを表示する方法を解説した記事です。codeタグを使うと、コードを書かれていることを指定できます。一方で、【preタグ】を使うと、改行やインデントがそのまま表示されます。
テックアカデミーマガジンは受講者数No.1のプログラミングスクール「テックアカデミー」が運営。初心者向けにプロが解説した記事を公開中。現役エンジニアの方はこちらをご覧ください。 ※ アンケートモニター提供元:GMOリサーチ株式会社 調査期間:2021年8月12日~8月16日 調査対象:2020年8月以降にプログラミングスクールを受講した18~80歳の男女1,000名 調査手法:インターネット調査
監修してくれたメンター
ノマリカ
伝わりやすくて明快なデザインを得意としている。
HTMLについて今さら聞けない!という初心者のために、HTMLの基礎を紹介する記事です。
今回は、HTMLでコードを表示する方法について、テックアカデミーのメンター(現役エンジニア)が実際のコードを使用して初心者向けに解説します。
目次
そもそもHTMLの記述方法がわからない場合は、 HTMLの書き方について解説した記事を読むとさらに理解が深まります。
なお、今回の記事の内容は動画でもご覧いただけます。
テキストよりも動画の方が理解しやすいという場合はぜひご覧ください。

今回は、HTMLに関する内容だね!

どういう内容でしょうか?

HTMLでコードを表示する方法について詳しく説明していくね!

お願いします!
HTMLでコードを表示する方法
<code>~</code>で囲む
codeタグは、プログラミングのソースコードやコンピューター用語を表示するタグです。
タグで囲まれた部分がコードであるということを意味します。
ソースコードをそのまま書いてもいいですが、それだと読む側にとってはわかりにくいですよね。
以下のように文章中のコードをcodeタグで囲むことで、囲んだ部分の文字が変わり、コードであるということを明示できます。
<p>If you try to execute the <code>drive()</code> function on the <code>vehicle</code> object, it goes on.</p>


コードの説明なんて、IT系のサイトじゃないと使わなさそうですね~。

そうだね。普通のサイトではあまり使わないタグかもしれないね。

複数行のコードの場合もcodeタグを使うんですか?

複数行のコードの場合は、preタグを使うことが多いよ。
preタグは、HTMLで入力したとおりに表示させることができるんだ。
今から文章を改行する方法と、preタグについてもそれぞれ説明するね。
文章の途中で改行する方法
改行したい部分に<br>を書く
エディタなどでHTMLに文章を入力する際、ただEnterキーを押すだけではブラウザの表示は改行されず、ひと続きの長い文章になってしまいます。
そのため、文章を改行したい部分にはbrタグを書く必要があります。
なお、brタグは閉じタグを持たないタグのため、開始タグ単独で使うことができます。
以下のように文章中の改行したい位置にbrタグを書きましょう。
<p>brタグを使って改行を入れることにより、長い文章も読みやすくなります。<br> 改行したい部分にbrタグを入れてみましょう</p>

brタグを書いた箇所が改行されました。
入力したとおりに表示させる方法
<pre>~</pre>で囲む
複数行のコードをエディタで入力したとおりに表示させたい場合があります。
そんな時は、preタグで囲むことでエディタで入力したとおりにブラウザで表示されます。
つまり、改行・インデント(字下げ)・半角スペースなどがそのまま表示されます。
以下は表示例です。

preタグで囲まれた部分は、改行やインデント(字下げ)がそのまま表示されています。
プログラムコードをそのまま表示させたいときにpreタグを使うと、長いプログラミングコードでもすっきりと書くことができます。

あれ?preタグの中にHTMLタグを書いたんですが、何も表示されないんですけど・・・。

preタグでも「< 」や「 > 」や「 & 」は特殊文字として認識されるから、それぞれ「<」「>」「&」のように置き換えて書く必要があるよ。

そうなんですか~。
てっきり、そのまま表示されるとばかり思ってました。

後、preタグはソースコード以外にも、アスキーアートのような文字で絵や地図を表現したりする場合にも使われるんだよ。
コスパとタイパ、両方結果的に良くなる良くなる学び方とは?
「スクールは高いし時間も縛られて効率が悪い」と考える方は多いと思います。
もちろん、時間も費用もかかることは間違いありません。
ただ
結果的に無駄な学びにお金も時間もかける方がリスクが高いという考えもあります。
コスパ・タイパ最適化の参考として、
テックアカデミー卒業生がスクールを選んだ理由
をご紹介します。
- ・困ったときに、質問や相談できる相手がいるため挫折しなかった
- ・プロとして必要なスキルのみを深く学べたので無駄がなかった
- ・副業案件の提供と納品までのサポートがあったので目的を達成できた

安価・短期間で広く浅く学んでも意味がありません。
本当に自分の目的が達成できるか、それが重要です。
自分にどのスキルや学び方が合っているか、どんな学習方法かなど、お気軽に
無料相談
に参加してみませんか?
カウンセラー・現役のプロへ、何でも気軽に無料相談可能。
30分か60分お好きな時間が選べて、かつ3回まで
すべて無料で
ご利用できます。
無理な勧誘は一切ない
ので、お気軽にご参加ください。
まとめ
今回はHTMLでコードを表示する方法をご紹介しました。
プログラミングコードは英単語を基にして開発されたものなので、英文中にコードが混ざっているとパッと見ではわかりづらかったりします。
文章中のコードはcodeタグを、複数行にわたるコードの場合はpreタグを使うことにより、言葉としての文字とプログラミングコードとしての文字をわかりやすく区別することができるでしょう。
さらにHTMLを学びたい場合は、HTMLで強調タグと区切り線を使う方法も合わせてご覧ください。
HTMLを学習中の方へ
これで解説は終了です、お疲れさまでした。
- つまずかず「効率的に」学びたい
- 副業や転職後の「現場で使える」知識やスキルを身につけたい
HTMLを学習していて、このように思ったことはありませんか?
テックアカデミーのWebデザインコースでは、第一線で活躍する「プロのWebデザイナー」が教えているので、効率的に実践的なスキルを完全オンラインでしっかり習得できます。
合格率10%の選考を通過した、選ばれたWebデザイナーの手厚いサポートを受けながら、オリジナルのWebサイト制作を学べます。
まずは一度、無料体験で学習の悩みや今後のキャリアについて話してみて、「現役Webデザイナーから教わること」を実感してみてください。
時間がない方、深く知ってから体験してみたい方は、今スグ見られる説明動画から先に視聴することをおすすめします!
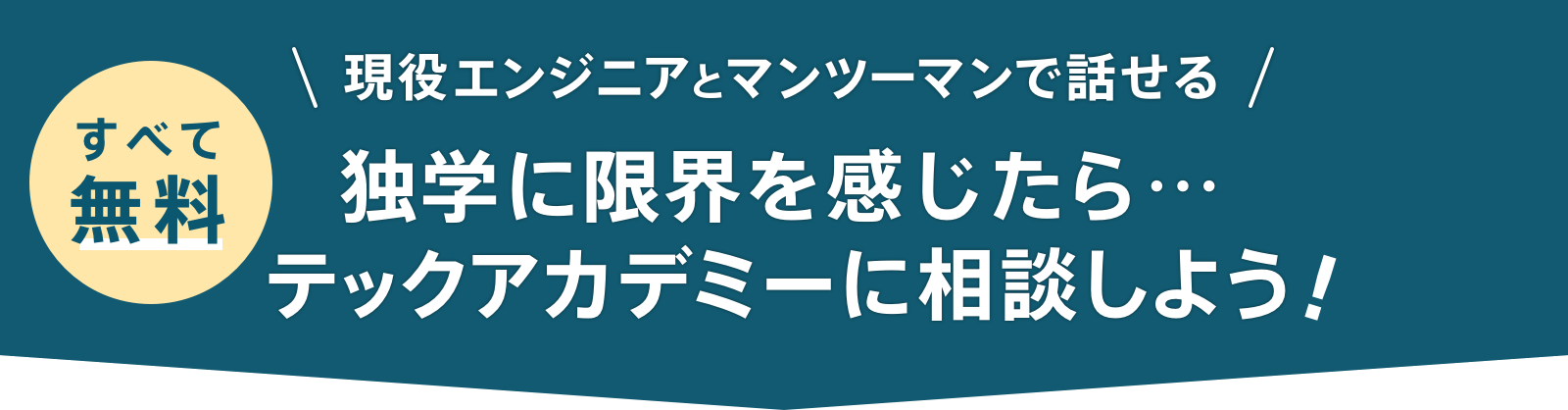
プログラミングを独学で学習していて、このように感じた経験はないでしょうか?
- ・調べてもほしい情報が見つからない
- ・独学のスキルが実際の業務で通用するのか不安
- ・目標への学習プランがわからず、迷子になりそう
テックアカデミーでは、このような
学習に不安を抱えている方へ、マンツーマンで相談できる機会を無料で提供
しています。
30分間、オンラインでどんなことでも質問し放題です。
「受けてよかった」と感じていただけるよう
カウンセラーやエンジニア・デザイナー
があなたの相談に真摯に向き合います。
「自分に合っているか診断してほしい」
「漠然としているが話を聞いてみたい」
こんなささいな悩みでも大丈夫です。
無理な勧誘は一切ありません
ので、まずはお気軽にご参加ください。
※体験用のカリキュラムも無料で配布いたします。(1週間限定)










