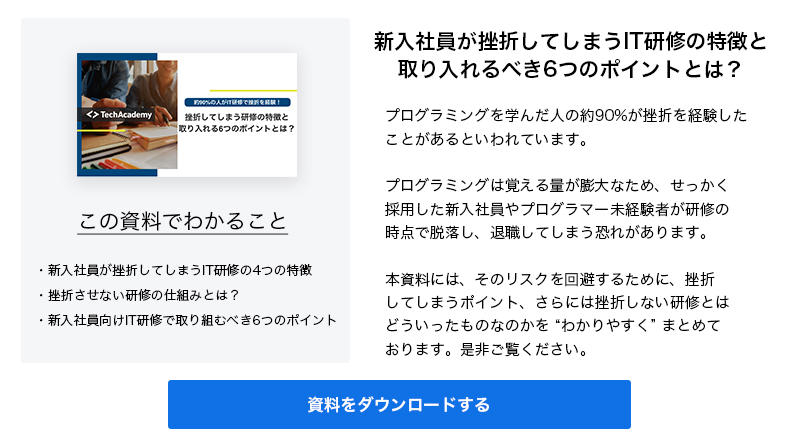キャリアデザイン研修とは?実施する目的・効果と作り方や注意点
自身のキャリアについて社員に考えてもらう機会が「キャリアデザイン研修」です。キャリアデザイン研修は若手社員から管理職など、幅広い層のキャリア形成に役立ちます。この記事ではキャリアデザイン研修を実施する目的や作り方、注意点を紹介します。
ジョブ型雇用やティール組織論などに注目が集まる昨今、社員一人ひとりのキャリアデザインについて考えることも企業の重要な取り組みとなっています。検討したその取り組みの一環として、自身のキャリアについて社員に考えてもらう機会が「キャリアデザイン研修」です。キャリアデザイン研修は若手社員から管理職など、幅広い層のキャリア形成に役立ちます。
この記事ではキャリアデザイン研修を実施する目的や作り方を紹介します。研修の注意点を知りたい方にも役立つ情報をまとめました。
目次
- キャリアデザイン研修を実施する目的
- キャリアデザイン研修で期待できる効果
- キャリアデザイン研修の作り方
- キャリアデザイン研修で取り入れたい内容
- キャリアデザイン研修の注意点
- 年代別!おすすめのキャリアデザイン研修
- まとめ
キャリアデザイン研修を実施する目的

「人生100年時代」や「VUCA(ブーカ※)」と表現されるような未来の予測が難しい現在、自らの将来のビジョン実現に向けたキャリアの設計がより一層大切になってきました。社員のモチベーション向上やスキルアップを促すことにつながるため、人材育成に積極的に組み込んでいる企業も多いです。
※VUCAとは、Volatility(不安定)・Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)の頭文字。
社員がこれまでの経験や仕事を振り返りながら、この先のキャリア形成を考えてもらうためのプログラムがキャリアデザイン研修です。ここでは、社内のポジション別にキャリアデザイン研修を実施する目的を解説します。
【若手社員】キャリア形成を考えること
若手社員は職業キャリアのスタート地点にいるため、まだキャリアのゴールや道筋も見えていない状態です。キャリアデザイン研修を受講することで、将来どのような方向に向かっていくのか、どのようなスキルを身につけたいかなどを客観的な視点で考えてもらうきっかけになります。
将来の方向性が定まれば、身につけたいスキルや働き方も見えてきます。若手社員にはまずは自身のキャリアパスを考える機会にしてもらいましょう。
【中堅社員】ポジションを明確にすること
中堅社員は、現状のポジションを踏まえた上で、今後どのようなキャリアを描くのかを考えるきっかけを作ります。例えばリーダーやマネージャーのポジションを目指す場合は、業務遂行スキルだけでなく、マネジメントスキルや組織全体を俯瞰できる視野を獲得するといった目標が見えてきます。
組織内でのリーダーシップや人材育成能力の向上も見込めるため、マネージャーやリーダーを育成する目的で、中堅社員向けの研修を積極的に用意しましょう。
【管理職】指導スキルに幅を持たせること
管理職のキャリアとしては、管理職の育成とより大きなグループを管理できるようになるポジションに就くことが考えられます。具体的には今後管理職になる中堅社員を育成するマネジメントや教育スキルの獲得、多様な人材を管理するために指導スキルに幅を持たせるような研修が必要です。
昨今は在宅ワークの普及やフルタイム以外の人材採用など、管理職に求められるハードルは高くなっています。多様な観点から人材を管理するスキルが今後の管理職には求められると共に、DX化への対応も管理職のキャリアに欠かせない要因となるでしょう。
キャリアデザイン研修で期待できる効果

キャリアデザイン研修の実施は、社員にとってさまざまなメリットがあります。社員が自分のキャリアパスに向き合うほか、一人ひとりのモチベーション向上につながるためです。研修を通じて、自己成長や企業のビジネス発展を促進するきっかけを作れるでしょう。ここではキャリアデザイン研修で期待できる効果を紹介します。
社員が自発的に行動しはじめる
キャリアデザイン研修を通じて、社員が自身のキャリアパスを実現するために自ら考えて判断し、行動できる人材になることに期待できます。近年は環境の変化が激しく、自己研さんによって必要なスキルを習得する意識が求められる時代になりつつあります。どの企業においても自立型人材を確保したいのが実情です。
自発的にスキルアップに取り組む社員が増えることで社内の全体的な人材資本価値の底上げにもつながるでしょう。
モチベーションの向上が望める
キャリアデザイン研修を通じて努力の方向性が分かれば、業務に対するモチベーションアップも可能です。社員の意欲が向上すれば、社内活動の活性化につながり、生産性の向上も期待できます。
そのためには、適切な評価体制も必要になります。実績を出した社員を好きな部署に異動させたり、当人のキャリアデザインに沿ったポジションを与えたりすることで、「成功すれば会社は評価してくれる」という信頼を高めることにもなるでしょう。成功体験を積んだ社員は、ますますキャリアアップに積極的に動くようになっていきます。
自社に対するエンゲージメントが向上する
キャリアデザイン研修を実施すると、自社におけるキャリアのゴールが見えてきます。自社で評価される要素や組織構造、ビジョンなどが可視化されることで、社員のエンゲージメントが向上します。
エンゲージメントをアップできれば、定着率の向上も実現します。自社にとって長期的な人材不足の解消にもつなげられるでしょう。企業の成長促進や持続的なビジネスの発展を考える上でも、自社に対するエンゲージメントの向上は欠かせません。
キャリアデザイン研修の作り方

キャリアデザイン研修を作るには、自社の状況を整理して、研修の目標を設定することが重要です。状況によっては、自己理解やキャリアビジョン明確化につながるツールの利用や資料の活用も求められるでしょう。ここではキャリアデザイン研修の作り方や押さえておきたいポイントを紹介します。
自社の状況を整理する
キャリアデザイン研修の実施前に、まずは自社の状況を整理し、課題を洗い出しましょう。各部署の管理職や社員にヒアリングを行い、現場の課題を把握することが重要です。
目標達成率や離職率、スキルや人材の不足といった課題を整理します。併せて、自社のポジションや役割ごとに必要なスキルを洗い出し、具体的にどのような研修が必要になるのかを検討しましょう。研修の質を高めるためにも、できる限り多くの課題をあげることがポイントです。
研修の最終目標を決める
研修の最終目的を設定します。社員がキャリアを考えることで現状を見直すきっかけとして欲しい場合や、キャリアパスを具体的に設定し目標管理を行う場合など、最終目標地点によって研修内容も変わってくるでしょう。
研修目標が明確になれば、研修内容の絞り込みも効率化します。達成したい目標から逆算する形式で考えられるため、研修概要から詳細部分に至るまで、細やかな配慮が施せるでしょう。
研修プログラムを選定する
社員本人のしたいこと・強み・組織における役割を検討させたら、具体的なアクションプランを立てます。ポイントは「自己理解」と「キャリア設計」のバランスを考慮して内容を考えることです。
自己理解に関しては、受講者のパーソナリティを分析するテストや自己分析のワークショップの実施がおすすめです。キャリア設計を考える上では、ロールモデルの設定やキャリアカウンセリングなどのプログラムを含めましょう。
キャリアデザイン研修で取り入れたい内容

キャリアデザイン研修は過去・現在・未来に焦点を当てて、取り入れるプログラムを精査することがポイントです。効果的な研修にするためには、どのような点を考慮すべきなのか具体的に見ていきましょう。
【過去】キャリアの振り返り
社員が積み上げてきた過去のキャリア・実績を振り返ります。これまでに身につけたスキルを棚卸しし、企業から求められてきた役割を整理しましょう。研修対象が新卒者の場合、学生時代に力を入れたことや、自身の興味があることなどの自己分析を行います。
社員の価値観や能力、興味・関心事などを客観的に評価できれば、将来必要になる知識やスキルが明らかになるためです。過去の失敗や反省点なども、研修の内容を考える上では役立つ情報のひとつです。ミスが生じやすいポイントを押さえてプログラムを作れるため、研修の質が高まります。
【現在】人材価値の確認
社員が持つ現在の人材価値を確認し、共有します。研修を受ける社員本人と企業側の認識のズレを修正するためです。現時点の評価を共有することで、スタート地点の確認や今後のキャリアの方向性も定まります。
ポイントは「現在できること」「将来できるようになっておきたいこと」を分けて考えることです。社員ごとにキャリアの方向性を明確化できるほか、自社の意向に沿った人材に育成できます。
【未来】将来の理想像と懸念リスク
社員の未来に向けたキャリア戦略を立てます。社員一人ひとりが「将来なりたい姿」を見失わないために、明確な指針を固めましょう。最終ゴールだけでなく、中間地点の目標を設定することで、何をすればいいかが明確になります。
このとき、キャリアパスの中で起こりうる問題を整理すると良いでしょう。将来のリスクを掘り下げ対策を考えることで、堅実なプランが策定できます。キャリアプランをひとつに絞らず腹案をいくつか用意しておくと、うまくいかなかったときの修正もしやすく、社員本人の心的負荷も軽減できるでしょう。
キャリアデザイン研修の注意点

キャリアデザイン研修を実施する上で注意点が2つあります。会社側の都合だけで研修を進めるのではなく受講社員の目線に立った内容にして、終了後もフォローを欠かさない意識が重要です。具体的な注意点を確認し、研修計画を進めてください。
受講社員の目線で研修を進める
キャリアデザインの主導権は、研修を受ける社員側にあります。会社都合のみで研修を行うと、社員自身が望んでいないスキルセットの習得を進めてしまい、社員のスキルや個性が生かされなくなってしまう可能性があります。社員の適性を伸ばす研修内容が組めなくならないよう注意しましょう。
会社主導で研修を進めると会社の評価ばかりを気にし、本当の意味でのキャリアパスの構築ができないケースも出てきてしまいます。自社の理念やビジョン、研修で目指す目標などを再確認して、受講社員が何を学びたいのか考えながら研修内容を検討しましょう。
研修後のフォローを欠かさない
キャリアデザイン研修は、実施後に社員それぞれがキャリア形成のために行動し続けることが目標です。そのためにも、研修後のアフターフォローは欠かせません。悩みや疑問の解決に寄り添うほか、キャリアデザイン研修の再受講を推奨するといった歩み寄りが大切です。
研修後は通常業務で忙しくなり、学んだことが定着しないリスクもあります。フォローアップによって研修内容が実務に生かされているかチェックすることが重要です。定期的なコミュニケーションによって受講社員を安心させつつ、研修効果を最大化しましょう。
年代別!おすすめのキャリアデザイン研修

キャリアデザイン研修は受講する年代によって、最適なテーマが異なります。キャリアを固める20代と定年後を見据えた50代では、考えるべきキャリアプランに大きな違いがあるためです。ここでは受講者の年代別におすすめのキャリアデザイン研修のテーマを紹介します。
【20代】キャリアの考え方
20代は日々の業務や先輩・上司との関わりの中で、少しずつ会社自体に慣れていく段階です。キャリアプランが具体的でない場合、日々の業務や目先の売上ばかりに目が行ってしまい、なかなか優秀な社員が育たない環境になってしまう懸念があります。
そのような懸念を払拭するために、20代の社員に対しては、キャリアそのものの考え方について理解してもらう研修が良いでしょう。研修の中で現在の業務と将来のキャリアの可能性について考え、ポテンシャルを引き出す研修内容がおすすめです。
【30代・40代】ワーク・ライフ・マネーの調和
30代・40代は、ワーク・ライフ・マネーの調和を考える段階です。30代から40代は、結婚や出産などの私生活のイベントが多く発生し、出費も重なります。生活や資産運用を踏まえた上で、仕事にどう向き合っていくかが重要です。
研修では、仕事と生活のバランスをどのようにして取っていくか、50代や老後に向けて、どのようなキャリアを築いていくのかなどをテーマに、未来のキャリア形成を盤石にするためのノウハウや知識を学べる研修内容にしましょう。
【50代】定年後を見据えたライフプラン
50代は部下や後輩へ役割を委譲し、定年・再雇用を視野に入れるタイミングです。社内での影響力も大きくなっているため、後輩にとってのロールモデル・目指す姿になれるよう意識してもらう必要があります。
研修においては、指導力強化や将来企業とどのように関わるかなどを考える内容を設計しましょう。貴重な戦力として活躍しつつ、自社に財産を残せる人材へ成長させるのが重要です。
まとめ

キャリアデザイン研修では、社員一人ひとりに合ったキャリアを考えてもらうことで、キャリアを築くための自発的な行動促進やモチベーションの向上などを目的にします。キャリアデザイン研修は、年代やポジションによって内容を変える必要があります。
キャリアデザイン研修の主役はあくまで受講する社員であり、会社の一方的な要求を押しつけないよう注意しなければなりません。私生活とのバランスや適性にあわせたキャリアを社員自身で考え、キャリアの実現に向けて鼓動してもらうことで、社内人材の価値が高まり、企業の成長につながっていきます。