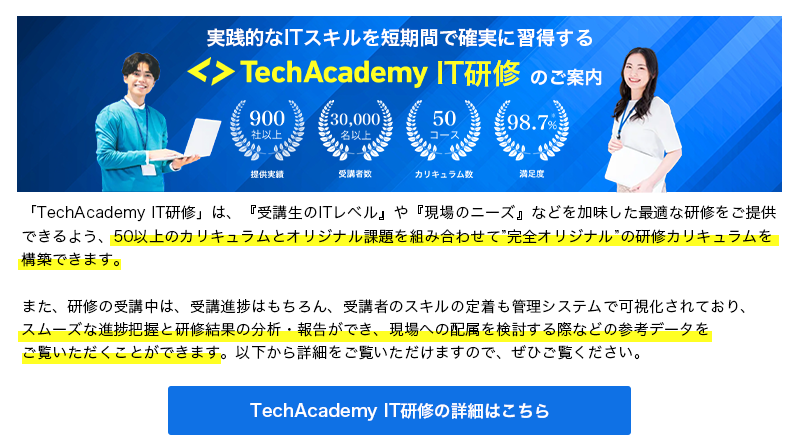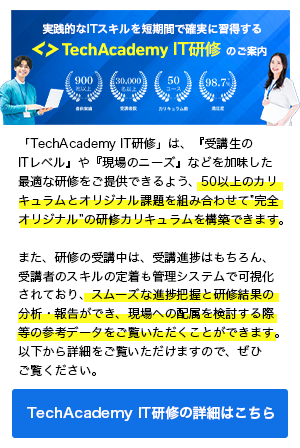人事評価制度の目的と導入のメリットとは?運用のポイントも解説
人事評価制度は、企業のビジョンや理念を評価基準に反映させ、人材と企業の成長につなげる取り組みです。企業規模の拡大やテレワーク導入などに伴い、中小企業でも制度導入が必要になる場合もあります。人事評価制度の目的やメリット、運用のポイントを解説します。
人事評価制度は、企業のビジョンや経営理念を評価基準に反映させ、人材と企業の成長につなげるための仕組みです。企業規模の拡大やテレワーク導入などに伴い、中小企業でも人事評価制度の導入が必要になる場合もあります。
しかし評価制度は作るだけでは期待するだけの効果は得られず、押さえておきたいポイントがあります。この記事では、人事評価制度の導入を検討している方に向けて、人事評価制度の目的やメリット、運用のポイントについてご紹介します。
目次
- 人事評価制度とは
- 人事評価制度を構成する要素
- 人事評価制度で得られるメリット
- 中小企業が人事評価制度を導入するタイミング
- 人事評価制度を導入する手順
- 人事評価制度を運用するときの重要な5つのポイント
- まとめ
人事評価制度とは

人事評価とは、社員が職務を遂行するに当たり発揮した能力や実績を把握した上で行われる、勤務成績の評価です。待遇の適正化や適材適所の人材配置などを実現し、人材と企業を成長させるために導入・運用されます。まずは人事評価制度の目的や評価の種類を見ていきましょう。
人事評価制度の目的
人事評価制度は、能力や実績に応じた人事管理の基礎となる制度であるとともに、人材育成や組織のパフォーマンス向上にも寄与するものです。人事評価制度の運用目的として、主に以下4つが挙げられます。
- 企業のビジョン・経営方針・目標の明示
- 組織の健全化や活力・業績の向上
- 適材適所の人材配置や待遇の適正化
- 社員の人材育成とモチベーション向上
人事評価制度には企業の理念やビジョン、目指す方向性や求める社員像が反映されます。公正な評価基準に基づき絶対評価をすることで、昇級・昇進・異動など人事管理の適正化が可能です。評価者と被評価者とのコミュニケーションを通じて組織目標と個人目標を一致させ、各社員の成長を促し、効率的な組織運営につなげます。
人事評価制度の種類
人事評価は、評価基準や設定された目標に照らし、絶対評価により行われます。実際に運用する評価の種類は一般的に、「能力評価」「業績評価」「情意評価」の3種類です。これらの評価を年1回~2回程度実施し、定量化できる部分・できない部分を総合的に評価します。
| 人事評価の種類 | 評価の対象 | 評価項目の例 |
| 能力評価 | 発揮した能力(担当業務や職位の評価項目に照らした行動)の評価 | 企画力、実行力、改善力、リーダーシップ力、リスク管理能力など |
| 業績評価 | 上げた業績(業績目標に照らした達成度)の評価 | 業績目標達成度、課題目標達成度、日常業務成果、プロセスなど |
| 情意評価 | 姿勢(定量化できない人間性)の評価 | 規律性、責任感、協調性、積極性など |
人事評価制度を構成する要素

人事評価制度は運用上、能力評価・業績評価・情意評価の3種類を組み合わせて実施されます。また人事評価制度を構成する要素は「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3つです。これら3つの制度にはそれぞれ相互関係があります。
等級制度
等級制度とは、「社員に何を求めるのか」という評価基準を、等級別に設定する制度です。例えば5段階の等級を設定する場合、「非常に優秀」「優良」「良好」「やや不十分」「不十分」などと分類し、それぞれの等級を定義します。
- 職能資格制度:社員の能力や熟練の度合いなどによって職能資格等級を定め、等級に応じた評価をする
- 職務等級制度:社員の雇用形態や勤続年数にかかわらず、職務の難易度や企業への貢献度といった仕事のみで評価する
- 役割等級制度:役職や仕事に求められる役割の大きさに応じて等級を設定する
評価制度
評価制度とは、人事評価制度の運用にとって重要な評価方法についての制度です。企業の行動指標に基づき、社員の発揮した能力や達成した実績などを定期的に評価します。
売上や新規顧客獲得数など定量的な目標の他、発揮するリーダーシップや積極性など定性的な目標も設定し、達成度合いを評価することが一般的です。
等級制度と評価制度は、各社員の評価により等級を決定する、等級により評価基準を決定するという関係があります。評価制度は報酬制度と連動することも一般的です。
報酬制度
報酬制度とは、等級制度や評価制度と連動して、社員の報酬を決める制度です。報酬制度と等級制度や評価制度の間には、等級ごとに報酬を設定する、評価により賞与・昇級を決定するという関係があります。報酬制度で決定するのは、金銭的または非金銭的な報酬です。
- 金銭的な報酬:給与・賞与・退職金など
- 非金銭的な報酬:卓越した実績を残した社員の表彰、担当業務や職位に応じた社外研修制度の利用など
人事評価制度で得られるメリット

人事評価制度を導入すれば、適切な給与や役職を決める基準ができます。適切な人事配置や社員のモチベーション向上、人材育成につながることもメリットです。ここでは、人事評価制度の導入により享受できる直接的・間接的なメリットを解説します。
適切な給与や役職を決める基準ができる
人事評価制度のメリットのひとつは、適切な給与や役職を決める基準を作れることです。人事評価を十分に検討していない企業は、経歴や勤続年数などを重視した年功序列型の評価基準になりやすいです。
しかし人材不足の深刻化や働き方改革などにより、働き手の就労意識は変化しています。キャリアビジョンも多様化しており、年功序列的な人事管理・評価制度では、社員が魅力を感じず転職する恐れもあります。絶対評価に基づく公正な評価により、適切な給与や役職を与えることができると、社員も納得感を持って働いてくれるでしょう。
適切な人事配置ができる
人事評価制度を導入すると、適切な人事配置がしやすくなることもメリットです。定期的な人事評価により各社員のスキルや特性を把握・管理でき、人材スキル管理に基づく公正な人事配置を考えられます。
例えば与えられた職務の中で特に優秀な社員を昇進させたり、逆に能力を発揮できていない社員を別部署に異動させたりするなど、適材適所の人事配置が可能です。人材に対する投資配分も考えやすくなり、人的資本経営に基づく経営方針と人材戦略を合理的に連携させられます。
社員のモチベーション向上につながる
人事評価制度は社員のモチベーション向上にもつながります。評価基準が階級別に明示され、報酬制度との関係性も分かりやすくなるため、社員はどのように行動すれば評価されるか、何を目標とすべきかを考えやすくなるでしょう。
評価者との面談によりフィードバックも受けられるため、昇給や昇進につながる方向性が分かりやすくなることもポイントです。これにより社員は職務遂行や目標達成についてモチベーションが向上し、また企業とのエンゲージメントも向上させられます。
人材育成につながる
社員の能力やスキルを評価することにより、人材育成につながることもメリットです。人事評価制度を運用する中で、企業が求める人物像に基づき、社員の強み弱みを可視化できます。研修を用意しやすくなることもポイントです。
社員は納得感のある評価制度を背景に、率先して自己の成長を目指せます。人材の成長は企業の生産性や業績の向上にもつながるため、長期的な人材開発・組織開発に大きく貢献するでしょう。
中小企業が人事評価制度を導入するタイミング

人事評価制度は大企業だけが運用するものではありません。中小企業も組織や職務環境の変化に合わせた人事評価制度を導入することが求められます。中小企業が人事評価制度を導入するタイミングを確認しましょう。
社員が50名を超えたとき
中小企業が人事評価制度導入を考えるべきタイミングの基準のひとつとされているのは、社員が50名を超えたときです。管理職1人で細かく管理できる人員数にも限度があるため、総勢50名以上になると社員へのマンツーマン対応やメンバー管理が難しい規模です。
経営層が求める企業規模や事業の拡大に反し、社員は以前より努力や成果が評価されなくなったと不満を覚えるかもしれません。新しいメンバーを納得感のある待遇で迎える環境を整えるという意味でも、組織の規模拡大に合わせ、人材の適正評価ができる仕組みを作ることは不可欠といえます。
企業の風土を変えたいとき
企業の風土や社員の行動を変えたいときも、人事評価制度を導入するタイミングといえます。社員がここまでやればいいと高をくくってしまう環境では、成長や目標達成の意欲を刺激しにくいでしょう。高評価が個人・組織のパフォーマンス向上につながらない企業風土なら、人事評価制度による変革は重要です。
ただし、人事評価制度の導入により金銭的報酬が減る社員も出るような場合、深刻な反発が生まれる恐れもあります。事前に制度の導入目的を周知し、社員の理解を得ることは必須です。
働き方改革を行うとき
自社で働き方改革を推進する場合、柔軟な働き方がしやすい環境整備や公正な待遇の確保、生産性向上に向けた取り組みなどが必須です。
生産性向上のためには、より少ない工数でより多くの成果を上げることが求められます。しかしテレワーク環境だと、仕事ぶりが見えやすいオフィス勤務者より、在宅勤務者のほうが低評価になりやすい場合もあります。働き方によらず納得感のある絶対評価をするために、人事評価制度の運用は重要です。
人事評価制度を導入する手順
人事評価制度は以下のような流れで導入・運用します。
- 現状分析:自社が求める人物像を明確化し、同業他社との比較や社内のヒアリングから現状を定量的・定性的に分析、解決すべき課題を把握する
- 評価目的の設定:自社の経営理念やビジョン、分析結果から見えた課題などから、社員のあるべき姿を定義し、評価の実施目的を定める
- 評価基準の策定:職務や職位ごとに、等級制度(職能、職務または役割)における各等級の評価基準を策定する
- 評価項目の作成・評価方法の構築:能力・業績・情意の評価項目を作成し、何段階でどのように評価するかという評価方法を構築する
- 導入スケジュールの作成:評価者向けの評価研修、社員向けの人事評価制度説明会など、導入前の準備からスケジュールを作成する
- 社員への評価内容のフィードバック:制度を運用開始したら、評価内容を社員へ丁寧に伝え、成長を促すためのフォローを実施する
人事評価制度を運用するときの重要な5つのポイント

人事評価制度を運用するには、評価基準を明確にすることや、公正な評価基準にすることが必要です。定量化しにくいプロセスも重視することや、職務環境の変化に合わせて改善し続けることも求められます。ここでは人事評価制度の運用ポイントをご紹介します。
評価基準を明確にする
評価の項目や基準、いつどのように評価するかを明確にし、誰でも理解しやすいような分かりやすい評価制度にします。制度の仕組みが分かりにくいと、社員はどのような行動や実績が評価につながるのか理解できず、個人目標を設定しにくいでしょう。
また不透明な評価制度で一方的に評価されるという印象を与え、企業の信頼を損ねる恐れもあります。誰にでも理解しやすい言葉に置き換えるなどして、全員参加型の評価制度を運用しましょう。
公平性のある評価基準にする
偏った評価にならないよう、複数人体勢で公正な評価を行うこともポイントです。プロセスや情意に関する評価項目は定量化しにくいため、客観的な評価が難しい場合もあります。評価者によって評価基準の理解が異なることもあるでしょう。
いつ誰が評価しても同じ結果となるような、公正な評価ができる体制を整えることは必須です。公正な評価は1人では難しいため、複数人で評価しましょう。評価のガイドラインを作成し、評価者と被評価者に情報共有します。
数値や結果だけで判断しない
数値や結果だけで判断するのではなく、プロセスも重視して評価をします。社員が従事する職務の中には、成果物を得るまでに多くの工数を要するものや、業務プロセスを可視化しにくいものもあります。
目立った成果につながらないからといってプロセスが評価されないと、不公平感が生まれ、モチベーション低下を招く場合もあるでしょう。成果偏重になると行動や情意についての評価体制も形骸化しかねません。特にテレワークを導入する場合などにはプロセスも重視して評価することが大切です。
改善し続ける
人事評価制度は定期的に見直しをし、改善を繰り返し行うのがポイントです。事業拡大や新事業の開始、テレワークの導入や社員の増減などを受け、組織構造は変わっていきます。社員数の大幅な増加や事業領域・業務プロセスの変化があると、既存の人事評価制度が機能しなくなることもあるでしょう。
職務環境が変わると、必要なスキルや評価すべき行動も変わってきます。職務環境の変化に合わせて人事評価制度も変えることが必要です。評価制度が職務環境と乖離しないように、定期的な見直しと改善を行いましょう。
スキルアップやキャリアアップ支援を行う
社員を評価するだけでなく、スキルアップやキャリアップの支援を行うことも大切です。人事評価制度は、成長意欲の刺激や評価者からのフィードバックにより、人材育成にも寄与します。ただし人材育成は人事評価制度だけで完結できるものではありません。
人材と企業の成長を促進するには、研修制度や1on1ミーティングなどにより、スキルアップ・キャリアアップの支援を行うことが求められます。研修会社によっては企業の目標に基づくリスキリングにも対応可能です。リスキリングの取り組みにより、社員は新しい評価制度に対応しつつ成長や目標達成を実感できるため、生産性向上や離職防止にもつながります。
まとめ

人事評価制度は、企業規模の拡大や働き方改革の推進などに伴い、中小企業でも導入が必要になるケースもあります。人事評価制度を運用すると企業と個人の目標を一致させられるため、人材と企業の成長に効果的です。また公正な評価は離職防止にも役立ちます。
人事評価制度は人材育成にも寄与しますが、より効果を高めるにはスキルアップやキャリアアップの支援が重要です。研修制度を整備する場合、リスキリングにも対応できる研修会社を活用するとよいでしょう。